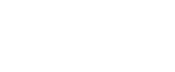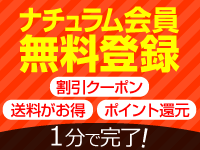2013年03月30日
※ ※ ※
どもども、こんにちはー。石川です。
※ ※ ※
今日ちょっと違った雰囲気でお送りいたします。
猛烈に長いので、お時間のある方はどうぞ。
※ ※ ※
もう会えない。だけど、きっと、幸せになってほしい。
彼女はきっときれいになっていくだろう。今よりもずっときれいになってしまうだろう。
それがとても嬉しくて、だけどとても切なくて。僕は・・・。
ぼんやりと彼女を眺めて言った。
いつもさ、背筋をぴんと伸ばしてるよね。
彼女はいつも、背筋をまっすぐにと伸ばして立っていた。
「小さいころからのクセなんです。へんですか?」
ううん。姿勢がよくてかわいく見えるよ。
黒目がちで大きな目が恥ずかしそうに僕を見た。
華奢な体を更に小さくした姿を見て、僕はもう一度、カワイイと思う。と、言った。
「たぶん、もう、一生分のカワイイを言ってもらった気がします」
そんなことないよ。今よりもっとかわいくなって、もっとカワイイって言われるよ。
僕はそう言って付け加えた。
カワイイね。
彼女が「もー」と言って、僕が笑った。やっぱりカワイイなって思いながら。
そんなに多くない思い出の中、彼女はいつも笑っていて、僕はその姿を見ている。
少し長めの前髪から黒目がちで大きな目がパチパチと瞬きし、嬉しそうに僕の方を見て、笑う。
僕が話しかけると彼女は少し驚いたように目を見開いて、僕の方を見る。
少し薄めのくちびるを開いて、「どうしたの?」って、
そう言いそうな明るい笑顔で僕に振り返る。
彼女はとても明るく、冬の陽だまりのように暖かだった。
それでも、彼女の世界は僕の側から一本の線が引かれていて、
そこから向こう側は新雪のように純粋で、
冬の空気みたいに澄んで見えた。
だけど、澄んだ空気のむこうにあるのは、精巧にできたジオラマのように
ひと気のない淋しそうな世界で、それを彼女が無理矢理に華やいで見せていた。
そして僕はそう演出された彼女の世界に一緒にいたかった。
僕と彼女は僕の小さな部屋でも隣り合わせて座った。
休みの日に僕らは並んで座って、昼間からビールを飲んだ。
飲んじゃおうか。僕が言って。「飲んじゃいましょう」と彼女が言った。
そんなときいつも、彼女の周りは優しいにおいがした。
それは女の人の香りとは違ったし、ましてや男性のにおいでもなかった。
「優しさがあふれているんです」彼女はそう言って笑い、僕はそんなバカなと言い、にらまれた。
僕らは隣り合わせで、部屋の壁を背もたれにして座った。
右利きの僕の右側、左利きの君の左側、二人の真ん中にはシロクマのぬいぐるみがあった。
右利きと左利き隣同士に座っていたから、僕の右手と彼女の左手がぶつかる。
そんなことがよくあった。
「あっ、逆に座った方がよかったですね。手がぶつかる」彼女はそう言った。
いや、いいよ。
僕たちはお互の利き手で手を繋ぐことができる。
「それなら利き手じゃない方で座った方がいいです。
そうしたら手を繋いだまま食べたり、お酒を飲んだりできますよ?」
・・・もう少し
「え?」
もう少しだけは、こうしていたい。
「相変わらず気持ち悪いこといいますね」
いつもの優しさがあふれ出したような暖かな笑顔を向けて彼女は言った。
好きという気持ちを忘れた。そう思っていた僕がやっと見つけたとても大切で、
この手に入れたかったもの。
安易な言葉に傷つけられていた彼女が大切にしたかった何か。
その二つを僕は同じものだと思っていたのかもしれない。
”いつか”や”今度”という間延びした言葉を嫌った彼女。
「そんな約束で傷ついたことがあります」と話してくれた。
そっか。と僕は言った。言葉に傷つけられていた彼女に対して、
僕は言葉で向き合うことができなかった。
彼女が僕に残した思い出が、今になって思い出される。
雪のように白い肌、まっすぐに伸びた背筋、くっきりと浮かぶ涙袋、
冬生まれの僕を褒めてくれたこと。
運転席に座る僕を見て、にっこリと笑い、僕の名前を呼んでくれた。
僕の顔を覗き込んだ彼女に少し疲れちゃったよ。
そう言うと、「春になったらいっぱい一緒にでかけましょうね」と、
僕の手をとってくれた。
僕がありがとう。と頭をなでると「子供みたいにしないでください!」と笑顔で怒った。
怒りながらも頭をなでているときには大人しく、嬉しそうにしていて、
自分でそれに気付いて「あやされてる!」と言って逃げた。
初めて会った時の思い出、いくつも交わした約束。
恥ずかしそうに少しだけ見せてくれた白い肌。
僕の腕の中で、僕の目をみて、彼女は一度だけ言った。
「わたしのこと、本当にすきですか?」
どう思い出しても、どんな場面を思い出してみても、彼女は笑っていて。
カップから溢れてしまう温かな、冬の日のココアのような笑顔しか浮かばないのだ。
僕らはいつも同じ部屋にいた。
しっかりと君を見て、僕は自分の気持ちを感じ、そして彼女にもそれを感じた。
僕たちはきっと同じ景色を見ていた。
一緒に過ごす日々を思うことで、僕は自分の気持ちを確かめた。
あまりに強く彼女を思っていたから。一緒に見ていたはずの景色に、
僕ら自身が映らなくなったのだ。
僕は頭の中で思い描いた自分と彼女を、僕たちそのものだと思っていたのかもしれない。
想像の中の僕はいびつで自分勝手な世界で彼女を守ろうとしていた。
僕の前でこぼした彼女の涙に気づかないまま、
つないだ手と手に幸せを、抱いたちいさな体に愛おしさを感じていた。
とても悲しいことだけど、僕が思う「大切にする」ことは彼女にとって愛情ではなく、
牢屋に入れられるのと同じ束縛だった。
厳重に閉じられた扉は冷たく、その部屋の中にいた彼女自身にとっては、
冷酷な他人の自分勝手な欲望そのものだった。
初めて僕の部屋にやってきたあの夜でさえも、
彼女は一人を感じていたにすぎなかった。
自分勝手な僕といるから独り。
そして彼女は疲れてしまったのだ。
いろいろなことに、強く。たくさんのことに、慢性的に。
一番近くにいたはずの僕は、彼女のことを守れなかった。
気づいてあげることさえできなかった。
僕はただ彼女のことを欲し、求めるばかりだった。
「もう、会えません」
送っていった多摩センターの駅で、僕が聞いたその声はいつもと同じ声で、
いつもの暖かな笑顔を見せた。それでもきっとそれは精一杯の笑顔で、
大きな目には涙をいっぱいにためていて、そこには初めて僕が、
自分のことばかり考えている僕がいた。
雪はきれいな雪景色を見せてくれた。でもそれは、春になり消えてしまった。
寒いところで生まれた彼女が、雪解けのようにひっそりと涙を流し、
そして、僕の目の前から消えてなくなってしまった。
最後に見た笑顔が、悲しいはずの雪解けが一番きれいだった。
そう、だから。
もうきっと会えないけれど、きっと、幸せになっていく彼女。
誰よりもかわいかった彼女が、きれいになっていくのが切なくて切なくて、だから。
きれいになってゆく彼女のことを、きっと幸せになる彼女のことを、
もう聞くことのできないあの笑い声と、二度と見ることのできないあの笑顔を、
黒目がちなの大きな瞳を、くっきり浮かぶ涙を、薄い唇を、
真っ白で折れてしまいそうな細い肩を、彼女を。
彼女のことも、本当の気持ちも僕は知ることもなかった。
僕には何も見えていなかった。
難しいことじゃなかった。ただ、二人で外の世界に飛び出せばよかった。
かつて、彼女を傷つけた”いつか”や”今度”という間延びした言葉ではなく
具体的な言葉を使って、これからの二人のことを話していけばよかった。
そこから始めていけばよかったのだ。
幸せにしてあげたかった。
できることなら僕の手で。そうなってほしかった。
彼女の嫌いな雨の降る夜、
新百合ヶ丘の駅にはあの日と同じように一つ、また一つと明りが灯りだして、
隣のイオンに張り合うように並ぶイトーヨーカドーの前を、
高校生ばかりが並ぶマクドナルドの前を、彼女が好きだった石釜ピザを焼くレストランの前を、
生姜料理専門店の前を、ビールやワインを買った酒屋の前を強く走った。
胸が詰まるくらいに、声にならないくらいに、涙を流しながら、僕は走った。
そうするしかなかった。
新百合ヶ丘の街の隅々が僕に尖った像を思い出させ、
僕はそのいちいちに胸を痛めた。アパートの狭い部屋のドアを閉めても、
記憶の断片が洪水のように押し寄せた。僕はドアに鍵を掛け、
そのままドアを背にうずくまり、しばらく動くことができなかった。
要約すると「sioux400を一度も使わず売ってしまったことを、後悔してる」って、
それだけでございますw
※ ※ ※
今日ちょっと違った雰囲気でお送りいたします。
猛烈に長いので、お時間のある方はどうぞ。
※ ※ ※
もう会えない。だけど、きっと、幸せになってほしい。
彼女はきっときれいになっていくだろう。今よりもずっときれいになってしまうだろう。
それがとても嬉しくて、だけどとても切なくて。僕は・・・。
ぼんやりと彼女を眺めて言った。
いつもさ、背筋をぴんと伸ばしてるよね。
彼女はいつも、背筋をまっすぐにと伸ばして立っていた。
「小さいころからのクセなんです。へんですか?」
ううん。姿勢がよくてかわいく見えるよ。
黒目がちで大きな目が恥ずかしそうに僕を見た。
華奢な体を更に小さくした姿を見て、僕はもう一度、カワイイと思う。と、言った。
「たぶん、もう、一生分のカワイイを言ってもらった気がします」
そんなことないよ。今よりもっとかわいくなって、もっとカワイイって言われるよ。
僕はそう言って付け加えた。
カワイイね。
彼女が「もー」と言って、僕が笑った。やっぱりカワイイなって思いながら。
そんなに多くない思い出の中、彼女はいつも笑っていて、僕はその姿を見ている。
少し長めの前髪から黒目がちで大きな目がパチパチと瞬きし、嬉しそうに僕の方を見て、笑う。
僕が話しかけると彼女は少し驚いたように目を見開いて、僕の方を見る。
少し薄めのくちびるを開いて、「どうしたの?」って、
そう言いそうな明るい笑顔で僕に振り返る。
彼女はとても明るく、冬の陽だまりのように暖かだった。
それでも、彼女の世界は僕の側から一本の線が引かれていて、
そこから向こう側は新雪のように純粋で、
冬の空気みたいに澄んで見えた。
だけど、澄んだ空気のむこうにあるのは、精巧にできたジオラマのように
ひと気のない淋しそうな世界で、それを彼女が無理矢理に華やいで見せていた。
そして僕はそう演出された彼女の世界に一緒にいたかった。
僕と彼女は僕の小さな部屋でも隣り合わせて座った。
休みの日に僕らは並んで座って、昼間からビールを飲んだ。
飲んじゃおうか。僕が言って。「飲んじゃいましょう」と彼女が言った。
そんなときいつも、彼女の周りは優しいにおいがした。
それは女の人の香りとは違ったし、ましてや男性のにおいでもなかった。
「優しさがあふれているんです」彼女はそう言って笑い、僕はそんなバカなと言い、にらまれた。
僕らは隣り合わせで、部屋の壁を背もたれにして座った。
右利きの僕の右側、左利きの君の左側、二人の真ん中にはシロクマのぬいぐるみがあった。
右利きと左利き隣同士に座っていたから、僕の右手と彼女の左手がぶつかる。
そんなことがよくあった。
「あっ、逆に座った方がよかったですね。手がぶつかる」彼女はそう言った。
いや、いいよ。
僕たちはお互の利き手で手を繋ぐことができる。
「それなら利き手じゃない方で座った方がいいです。
そうしたら手を繋いだまま食べたり、お酒を飲んだりできますよ?」
・・・もう少し
「え?」
もう少しだけは、こうしていたい。
「相変わらず気持ち悪いこといいますね」
いつもの優しさがあふれ出したような暖かな笑顔を向けて彼女は言った。
好きという気持ちを忘れた。そう思っていた僕がやっと見つけたとても大切で、
この手に入れたかったもの。
安易な言葉に傷つけられていた彼女が大切にしたかった何か。
その二つを僕は同じものだと思っていたのかもしれない。
”いつか”や”今度”という間延びした言葉を嫌った彼女。
「そんな約束で傷ついたことがあります」と話してくれた。
そっか。と僕は言った。言葉に傷つけられていた彼女に対して、
僕は言葉で向き合うことができなかった。
彼女が僕に残した思い出が、今になって思い出される。
雪のように白い肌、まっすぐに伸びた背筋、くっきりと浮かぶ涙袋、
冬生まれの僕を褒めてくれたこと。
運転席に座る僕を見て、にっこリと笑い、僕の名前を呼んでくれた。
僕の顔を覗き込んだ彼女に少し疲れちゃったよ。
そう言うと、「春になったらいっぱい一緒にでかけましょうね」と、
僕の手をとってくれた。
僕がありがとう。と頭をなでると「子供みたいにしないでください!」と笑顔で怒った。
怒りながらも頭をなでているときには大人しく、嬉しそうにしていて、
自分でそれに気付いて「あやされてる!」と言って逃げた。
初めて会った時の思い出、いくつも交わした約束。
恥ずかしそうに少しだけ見せてくれた白い肌。
僕の腕の中で、僕の目をみて、彼女は一度だけ言った。
「わたしのこと、本当にすきですか?」
どう思い出しても、どんな場面を思い出してみても、彼女は笑っていて。
カップから溢れてしまう温かな、冬の日のココアのような笑顔しか浮かばないのだ。
僕らはいつも同じ部屋にいた。
しっかりと君を見て、僕は自分の気持ちを感じ、そして彼女にもそれを感じた。
僕たちはきっと同じ景色を見ていた。
一緒に過ごす日々を思うことで、僕は自分の気持ちを確かめた。
あまりに強く彼女を思っていたから。一緒に見ていたはずの景色に、
僕ら自身が映らなくなったのだ。
僕は頭の中で思い描いた自分と彼女を、僕たちそのものだと思っていたのかもしれない。
想像の中の僕はいびつで自分勝手な世界で彼女を守ろうとしていた。
僕の前でこぼした彼女の涙に気づかないまま、
つないだ手と手に幸せを、抱いたちいさな体に愛おしさを感じていた。
とても悲しいことだけど、僕が思う「大切にする」ことは彼女にとって愛情ではなく、
牢屋に入れられるのと同じ束縛だった。
厳重に閉じられた扉は冷たく、その部屋の中にいた彼女自身にとっては、
冷酷な他人の自分勝手な欲望そのものだった。
初めて僕の部屋にやってきたあの夜でさえも、
彼女は一人を感じていたにすぎなかった。
自分勝手な僕といるから独り。
そして彼女は疲れてしまったのだ。
いろいろなことに、強く。たくさんのことに、慢性的に。
一番近くにいたはずの僕は、彼女のことを守れなかった。
気づいてあげることさえできなかった。
僕はただ彼女のことを欲し、求めるばかりだった。
「もう、会えません」
送っていった多摩センターの駅で、僕が聞いたその声はいつもと同じ声で、
いつもの暖かな笑顔を見せた。それでもきっとそれは精一杯の笑顔で、
大きな目には涙をいっぱいにためていて、そこには初めて僕が、
自分のことばかり考えている僕がいた。
雪はきれいな雪景色を見せてくれた。でもそれは、春になり消えてしまった。
寒いところで生まれた彼女が、雪解けのようにひっそりと涙を流し、
そして、僕の目の前から消えてなくなってしまった。
最後に見た笑顔が、悲しいはずの雪解けが一番きれいだった。
そう、だから。
もうきっと会えないけれど、きっと、幸せになっていく彼女。
誰よりもかわいかった彼女が、きれいになっていくのが切なくて切なくて、だから。
きれいになってゆく彼女のことを、きっと幸せになる彼女のことを、
もう聞くことのできないあの笑い声と、二度と見ることのできないあの笑顔を、
黒目がちなの大きな瞳を、くっきり浮かぶ涙を、薄い唇を、
真っ白で折れてしまいそうな細い肩を、彼女を。
彼女のことも、本当の気持ちも僕は知ることもなかった。
僕には何も見えていなかった。
難しいことじゃなかった。ただ、二人で外の世界に飛び出せばよかった。
かつて、彼女を傷つけた”いつか”や”今度”という間延びした言葉ではなく
具体的な言葉を使って、これからの二人のことを話していけばよかった。
そこから始めていけばよかったのだ。
幸せにしてあげたかった。
できることなら僕の手で。そうなってほしかった。
彼女の嫌いな雨の降る夜、
新百合ヶ丘の駅にはあの日と同じように一つ、また一つと明りが灯りだして、
隣のイオンに張り合うように並ぶイトーヨーカドーの前を、
高校生ばかりが並ぶマクドナルドの前を、彼女が好きだった石釜ピザを焼くレストランの前を、
生姜料理専門店の前を、ビールやワインを買った酒屋の前を強く走った。
胸が詰まるくらいに、声にならないくらいに、涙を流しながら、僕は走った。
そうするしかなかった。
新百合ヶ丘の街の隅々が僕に尖った像を思い出させ、
僕はそのいちいちに胸を痛めた。アパートの狭い部屋のドアを閉めても、
記憶の断片が洪水のように押し寄せた。僕はドアに鍵を掛け、
そのままドアを背にうずくまり、しばらく動くことができなかった。
要約すると「sioux400を一度も使わず売ってしまったことを、後悔してる」って、
それだけでございますw
Posted by 石川 at
11:10
│Comments(16)